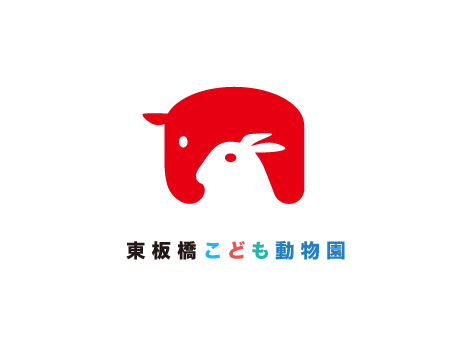top of page

The book of Josef et Anni Albers, whose exhibition held at Musée d'Art Moderne de Paris 2021
The book of Josef et Anni Albers, whose exhibition held at Musée d'Art Moderne de Paris 2021
1986年駒形克己により設立。グラフィックデザイン全般。本の制作・出版。商品開発。日本国内、世界各地で行われるワークショップ活動、展示プロデュースなど。1994年より世界各地を巡回している「1,2,3...KOMAGATA」展の開催や、毎年春に開催されるボローニャ国際児童図書展での、ブース「SMALL WORLD」の出展など。NY ADC銀賞、ラガッツィ賞、グッドデザイン賞(積み木)、グッドデザイン賞・ユニバーサルデザイン大賞、 ドミュメンタリー番組「触れる 感じる 壊れる絵本 ~造本作家・駒形克己の挑戦~」がWOWOWプライムにて放送され国際エミー賞にノミネート 他
デザインは光合成
植物は、二酸化炭素を吸収して酸素に変換。動物は酸素を燃やしエネルギーを得て行動する。造本と言う本づくりもまたこの手法。取材・観察による情報収集、それらをシンプルに凝縮。そして興味という心に作用する表現に変換して読者に経験がもたらせる形態に。それが私たちの本づくりです。
現場からうまれる
デザインは「つくる」よりも、「うまれる」ものだと私たちは考えます。常に対象者と向き合うことで、彼ら(クライアント)の畑(フィールド)を共有し、共に耕し問題提議をする、そこから芽吹くものが発想となりデザインとなります。まず現場に赴き、問題を察知。それがデザインの第一歩となります。
現場からうまれる
デザインは「つくる」よりも、「うまれる」ものだと私たちは考えます。常に対象者と向き合うことで、彼ら(クライアント)の畑(フィールド)を共有し、共に耕し問題提議をする、そこから芽吹くものが発想となりデザインとなります。まず現場に赴き、問題を察知。それがデザインの第一歩となります。
再生
3つのデザイン
1. Updated
2. Right on target
3. Far out
デザインを提案する際に常に意識することに「3つのデザイ��ン」があります。一つ目は、これまでのデザインをひき継ぎ、成功している部分を尊重しながらデザインを更新する、Updated Design。二つ目は、ターゲットに的確にヒットするデザイン、Right on target Design。そして三つ目は、将来を見据え一歩先行くデザイン、Far out Design。デザインには、こうした時間軸を取り入れていくことが絶えず求められています。
問題解決
1980年代初頭のニューヨークで経験したデザインは、問題解決そのものでした。単一言語の日本と異なり、言語と文化、人種が混在する社会では、コミュニケーションにおける重要なメタファーとなる視覚言語。視覚的な問題解決は社会的側面にも効用し、例えば企業や組織のロゴは、その活用次第で最小で最大の広告に。成功しているものが時代に合わせたゆるやかな更新が必要な一方で、そうでない場合には大胆な改変が新たなチャンスを創出します。
bottom of page